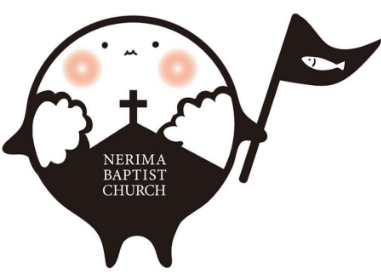世界中で最も読まれている書物『聖書』から、人生の真理を思い巡らします。
第一礼拝・第二礼拝は同じメッセージです。
礼拝の時間について、ここをクリックして確認できます。
ルカの福音の講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 23章26-43節
キリストなら自分を救え
35 民衆は立って眺めていた。議員たちもあざ笑って言った。「あれは他人を救った。もし神のキリストで、選ばれた者なら、自分を救ったらよい。」
36 兵士たちも近くに来て、酸いぶどう酒を差し出し、 37 「おまえがユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」と言ってイエスを嘲った。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- クレネ人シモンと女性たち
クレネ人シモンがイエスの十字架を運ばされることは、マタイやマルコも記しています。
自分の十字架を運べないほど痛めつけられたイエス。イエスが限界だったので、シモンとの関わりが生まれました。
続けて、シモンの後にイエスのために泣く大勢の女性たちがいたことを記すのはルカの特徴です。
ローマ軍によるエルサレムの破壊の日、兵士だけでなく、女性も子供たちも容赦なく、苦しむことになるのです。
イエスは死ぬ間際でも、弱い人たちを心配します。
- 侮辱されるイエス
誰もイエスが救い主だと気づかず「自分を救ったらいい」と罵ります。これほど惨めな救い主などいるはずがないと。
詩篇22篇で正しい人が不当な苦しみを受ける祈りで述べられている通りです。
「7私を見る者はみな 私を嘲ります。口をとがらせ 頭を振ります。
8 「主に身を任せよ。助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ。 彼のお気に入りなのだから。」
この祈りをユダヤ人は皆、知っていたでしょう。しかし、目の前にいるイエスが不当な苦しみを受けているとは思いもしませんでした。
- わたしと共にパラダイスに
イエスは失われた人を探し、救うために来たと言われました。
イエスの使命は、自分自身を救うことではなく、この世界で栄誉を受けることでもなく、失われた人を救うために自分の人生を捧げるのです。
死を前にして赦しを祈るイエスの姿が1人の罪人の人生を変えたのでしょう。
息を引き取る間際であっても、イエスは失われた人を探し、救いました。
「私を思い出してください」とイエスに声をかけた犯罪人をイエスは確かに迎えました。
■一緒に考えてみましょう
・3本の十字架がこの世界の現実であり、教会の現実です。神様は私に今日、どこに注目するように促しているでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 22章54-71節
イエスの眼差しは愛情
61 主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、「今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないと言います」と言われた主のことばを思い出した。
62 そして、外に出て行って、激しく泣いた。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- イエスはどのように見つめたか
新改訳2017の聖書学者たちは「見つめられた」に注をつけました。注にはルカ7:13とあります。
「主はその母親を見て深くあわれみ、「泣かなくてもよい」と言われた。」
母親に向けられたイエスのあわれみの眼差しを思い出しなさいと聖書の翻訳者はアドバイスします。
確かに、イエスはペテロの信仰がなくならないように祈り、立ち直ったら、力づけてやりなさいとも言われました。
私たちの救い主、主イエス・キリストとは、私たちの弱さを知り、見捨てるのではなく、憐れみ、愛情をもって、見つめてくださるお方です。
- 愛情の中で、泣こう
主イエスはペテロの失敗をご存じです。私たちの失敗も知っています。弱さ、傷つきやすさ、もろさ、足りなさ、全部、わかっています。
「わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈った」とペテロに言われました。
ペテロのように、私たちが失敗して、もう立ち上がれない、心底、自分に失望してしまう日があれば、ペテロと一緒に激しく泣いていいと思います。
絶望の涙はイエスの温かい眼差しによって、守られています。
- さまざまな罪が重なっていく
主イエスに従いきれないペテロ、悪ふざけがすぎるローマ兵、真理を本気で調べるよりも自分の都合のいいことだけを調べる指導者たち。
さまざまな罪がイエスの十字架を十字架につけるまでに、表に出てきます。
どれも私たちの日常にもあるかもしれません。
このような罪がイエスを十字架に追いやりますが、イエスの十字架はこのような罪の束縛から私たちを自由にしてくださいます。
■一緒に考えてみましょう
・私たちの見られたくない瞬間をイエスに見られるとしたら、どんな感じがするでしょうか。私たちの気まずさ、神の愛情を想像してみましょう。
ルカの福音の講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 22章39-53節
窮地で何を求めるでしょう
42 「父よ、みこころなら、この杯をわたしから取り去ってください。しかし、わたしの願いではなく、みこころがなりますように。」
(聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会)
■アウトライン
- 誘惑を受けるだけか、陥るか
誘惑を受けることと、誘惑に陥ることは大きな違いがあります。誘惑はイエスも受けました。
誰もが受けます。多くの場合、誘惑を受け、誘惑に陥ってしまいますが、誘惑に陥らないようにとイエスは言いました。
誘惑を受けたとき、神にしがみつけるのか、神から身を引いてしまうのか。
祈りは神の土壌に根を張り、試練の風が信仰を揺さぶる日に、しっかりと支えてくれます。これが祈りの力です。
- みこころがなりますように
「みこころ」という言葉が繰り返されます。祈りを突き詰めていくと「みこころがなりますように」にたどり着くのかもしれません。
ルカの福音書はマリアの祈りで始まりました「私は主のはしためです。
どうぞ、あなたのおことばどおり、この身になりますように」これもみこころを求める祈りです。
みこころを求めるイエスのために、天から、御使いが現れ、イエスを力づけるのです。
通らなければならない道なので、この状況を変えるのではなく、この状況の中、忍耐し、耐える力を与えてくださるのです。
- 暗闇の力
ユダも、弟子たちも、指導者たちも、皆、自分の正しさを疑うことなく、行動しています。
しかし、彼らが信じていたものは偽りの正しさでした。ユダは先生と仰いだイエスを偽りの口づけで裏切ります。
弟子たちは剣でイエスを守ろうとします。イエスから、許可を得る前に、切りかかりました。
弟子たちは、自分たちの力で、切り抜けようとします。イエスを逮捕しに来た指導者たちも偽りの正しさに支配されています。
昼の公の場ではなく、夜の隠れた場所で逮捕します。悪魔が真理を隠しました。
■一緒に考えてみましょう
・祈ることを知っていることは私たちにとって大きな力になります。祈りを通して、どんな神の働きを体験してきたでしょうか。思い出してみましょう。
説教者:片山 信彦 兄
聖 書:ヨハネの福音書21章1節~9節、13節
復活の主と共に歩む
■アウトライン
1. (21:4)この時の弟子たちはイエスが十字架で死なれたので、がっかりして先が見えない不安な状態だったのではないかと思います。
そこで、自分達のふるさとのガリラヤに帰りました。プロの漁師だったイエスの弟子たちが一晩中、暗闇の中でも働いても何の収穫もなく朝を迎えたのです。この漁にはイエスは同行していません。イエス不在の漁は何の収穫もなかったのです。
ですから、弟子たちは、がっかりし、疲れ果てて岸に戻ってきたと思います。
その時、イエスが岸に立っておられたのです。それは偶然イエスが岸辺に立っていたのではなく、弟子たちを待っていたのです。
私たちも一生懸命働いても何の収穫もない、良い結果が出ないという時があります。
人につまずいて失望したり、誤解されたり、ただただ疲れて、いつまでこの状態が続くのだろうかと悲嘆にくれながら帰る時もあります。
やっとの思いで船を降りて岸辺に着いた弟子たちのように、疲れ果てて家に帰り着くという時もあるでしょう。
でも、そこでイエスは待っていて私たちを迎えてくださる、というのが本日の最初のメッセージです。
2. (21:6)その様な弟子たちに向かって、イエスは、船の反対側、右側に網を打ちなさいと語り掛けます。
そうすると大漁でした。収穫が多くて引き上げることができないくらいの大漁でした。
自分の経験や知識ではなく、復活のイエスの言葉を聞いて船の反対側に網を降ろすという簡単なことを行うだけで大きな収穫を得ることができたのです。
私たちも、ちょっとしたことで良いことが沢山起きて、喜びに満たされることがあります。
苦労してきたことが報われたり、嬉しい出来事が起きたりします。
ただただイエスの言葉に従い、少し発想を変えたりするだけで、上手くいくことがあります。
たとえそれが小さな行動でも心が躍るような豊かな経験をすることがあります。
このことは、失敗や挫折の中で、イエスの言葉に従うことの大切さとその結果の幸いを示しています。
それがこの個所から学べる第二のことです。
3. (21:7)裸同然の格好をしていた弟子のペテロは、イエスが来られたので恥ずかしくなって湖に飛び込んだのでした。
「裸同然」というのは自分のすべてがさらけ出されている状態を象徴的に現わしています。
隠すことができない自分の恥ずかしい部分も見られてしまうことです。
私たちは誰でも他人に知られたくない部分があります。
人知れず自分のなしている事や、思っている事、心の内側などのすべてが明るみに出されたら恥ずかしくて逃げ出したくなる、隠したくなるものです。
実は、その恥ずかしい部分もイエスは知っていて、それでも私たちに寄り添って共に歩んでくださる方です。
それが今日学びたい三つ目のことです。
4.(21:13)を見ると、弟子たちを迎えて、パンと魚をとり弟子たちにお与えになったとあります。
この時の弟子たちがイエスを囲んで食事をしている光景を想像できますか? みんな満足して、笑顔の食事風景でしょうね。
この弟子たちとの食事風景を拡大すると私は、5 つのパンと 2 匹の魚で 5,000 人を養われた、あの給食の風景と重なります。
そして、この光景はイエスと共に食事をする聖餐式を思い起こさせます。
イエスは、火を起こして食事の支度をして、祝福の食卓を用意して私たちを歓迎して待っておられる方です。
最善が用意されていることに安心して、復活の主と共に歩む者でありましょう。
そして、私たちもこのイエスの姿勢に倣って少しでも他者に寄り添い、共に歩む者でありたいと願うのです。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 22章21-38節
奉仕する王の背中を見る
37 あなたがたに言いますが、
『彼は不法な者たちとともに数えられた』と書かれていること、それがわたしに必ず実現します。わたしに関わることは実現するのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 力の使い方
「人の子を裏切るその人はわざわいです。」(22節)という厳しいイエスの言葉が語られた後の弟子たちは、イエスの言葉を十分に受け止めずに、
人のことに意識が向きます。自分自身が、まず神の言葉を受け止めるスペースを作り、応答することから始めたいのです。
神の国での偉大さは、支配ではなく奉仕です。この世では奪う力、支配する力が大事かもしれませんが、神の王国では、分かち合う力が大切です。
神の王国を実現する力の使い方を学ぶように私たちはチャレンジを受けています。
- 立ち直ったら、力づけて
この後、サタンが全力で襲いかかってきます。弟子たち皆が、サタンの攻撃を受けます。
しかし、イエスは弟子たちが猛攻撃にさらされても、信仰がなくならないように祈ってくださいました。
神は弟子たちの裏切り、失敗を知っています。人にとっては恥であり、絶望かもしれません。
それでも、「戻ってきなさい」が神の思いです。わたしはあなたを待っている。
「立ち直ったら、神の家族を力づけなさい」とペテロに務めを託します。
- 不法な者たちとともに数えられた
これから時代が明らかに変わります。37節の引用はイザヤ書53:12。
イエスの十字架の意味を理解するために重要な「苦難のしもべ」と呼ばれる預言の一部です。
不法な者とは、律法に従わない者という意味で、神に従わない人たちと共にイエスは数えられることが告げられます。
イエスが世からそのように拒絶されるなら、弟子たちもまたそのような拒絶を受けるでしょう。
最後の晩餐からわかるのは、人間の失敗はあちこちにあるにもかかわらず、神の計画は着実に進んでいくことです。
■一緒に考えてみましょう
・「わたしの父がわたしに王権を委ねてくださったように、わたしもあなたがたに王権を委ねます」というイエスの約束をどのように受け止めているでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 22章1-20節
これがリアルな最後の晩餐
19 それからパンを取り、感謝の祈りをささげた後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。
「これは、あなたがたのために与えられる、わたしのからだです。わたしを覚えて、これを行いなさい。」
20 食事の後、杯も同じようにして言われた。「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による、新しい契約です。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ユダの裏切り
ユダがなぜ裏切ったのか。サタンが入ったとだけ記しました。それ以上のことをルカは語りません。
十二弟子のうちの一人が、どのような理由であれ、イエスを裏切った。
これがこの世界のリアルであり、イエスはこの世界をこのままにするのではなく、想像を絶する苦しみを引き受けてでも、
この世界を助けるために、神の使命に従っていくのです。
イエスの生きた時代も、私たちが生きる時代も、恵みと罪、聖さと情けなさ、忠誠と裏切り、
すべてが一つの地平に広がっています。ここで私たちは生きなければなりません。
- 切に願った時間
イエスはこの食事を切に願っていたと言われます。
かつて、あのエジプトから救い出してくださった神様が私たちの神であると祝うこの食事をイエスは誰よりも楽しみにしていました。
目の前には苦しみが迫っています。来年、一緒に過越の祭りを祝うことはないと知っています。
それでも、弟子たちと一緒に神の救いをお祝いことをイエスは心待ちにしていました。
- 過越の祭りに新しい意味を
エジプトでは、子羊の血をふりかけられた家は災いが過ぎ去りました。
過越の子羊の代わりに十字架で裂かれるイエスの体が弟子たちに与えられ、血が流され、新しい契約が結ばれるのです。
この後、聖餐式を行います。「覚えて、行いなさい」というイエスの言葉は、12弟子と一緒に、私たちが今ここでパンと杯をいただき、イエスの愛を受けるということです。「あなたがたのための」という言葉は主にある教会の一致を強め、来るべき時代への準備をさせてくれます。
■一緒に考えてみましょう
・聖餐式という主イエスの食卓に招かれ、今日はどのように感じたでしょうか。
ルカの福音の講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 21章20-38節
チコちゃんに叱られる!?
35 その日は、全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。
36 しかし、あなたがたは、必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 終わりに向かうとは
エルサレムの滅亡が語られた後、終わりのことについてイエスは語られます。
諸国の民が不安に陥ると書かれているように、人々は自然を前に、無力さを痛感し、途方に暮れるような感覚に襲われます。
天地が揺らぐイメージが語られ、次に「人の子」という非常に重要な専門用語が出てきます。
「人の子」というのは旧約聖書の預言の一つです。ダニエル書7章に出てきます。
異教徒によって苦しめられた後に、神の民はあがなわれる時について語られていると信じられていました。
- 終わりに向かう教会の希望
1イエスが宣教の中で神の国の権威を示すとき、2十字架と復活について話すとき、3再臨、
つまり再びイエスが戻ってくることを語るときに「人の子」をイエスは使いました。この文脈では、終わりのとき、
神の王国の権威を持って来られるイエスを指しています。
特に、ルカがここで伝えたいメッセージは、苦しんでいる民にあがないをもたらすためにやって来ることを強調しています。
迫害が起こると予告されました。でも、必ずイエスが来られるから、待ち望みなさい。終わりに向かって歩む教会へのイエスの励ましです。
- 生活が祈りとなりますように
日々の暮らしがどのようなものであるか、イエス様はご存じです。
だから、心が、放蕩し、ほしいままに流されたり、酒などに酔わされ、注意力が失われたり、生活の思い煩いで心が占められて、
そこにイエス様のスペースがなくなることがないようにという言葉を、しっかり受け取りましょう。
私たちの生活そのものが神への捧げものであり、祈りとなりますように。
■一緒に考えてみましょう
・終わりは突然、訪れるということを、どのようにして日々、意識することができるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書21章5-19節
忍耐が必要な季節
17 また、わたしの名のために、すべての人に憎まれます。
18 しかし、あなたがたの髪の毛一本も失われることはありません。 19 あなたがたは、忍耐することによって自分のいのちを勝ち取りなさい。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 美しい神殿の内側の腐敗
当時の神殿はヘロデ大王が改修工事を始め、その美しさに人々は圧倒されましたが、イエスは内側の腐敗を見抜き、悔い改めないので、滅びると語りました。イエスの時代が紀元30年代としたら、ローマ軍によってエルサレム神殿が破壊される紀元70年ごろまでの出来事としてこの場面を読んでいきます。
ユダヤ民族がローマに対して反乱を起こし、ローマ軍によって神殿は徹底的に破壊される将来に備えるようにとイエスは語ったのです。
- 迫害の中で、授けられる言葉
エルサレムが滅びる前に、弟子たちを待ち受けているのが迫害です。使徒の働きには初代教会に対する多くの迫害が記されています。
迫害はイエスの弟子として生きる時、避けては通れません。迫害はイエス・キリストを証する機会となります。
語る言葉もイエスが用意してくださると約束が与えられます。これは旧約時代から、神が何度も約束してきたことです。
モーセに話す言葉を与えた神は、私たちにも知恵の言葉を与えてくれます。
「今、行け。わたしがあなたの口とともにあって、あなたが語るべきことを教える。」(出4:12)
- 迫害は起こるもの
迫害が起こるというイエスの言葉を私たちは注意深く読みましょう。
イエスが語っていたと知らなければ、迫害が起こったときに、物事が悪い方向に進んでしまったと心配してしまうかもしれません。
迫害に遭う前に、イエスは弟子たちに警告しました。
「誰にも惑わされるな」、「自分の話をするチャンス」、「知恵を授ける」、「忍耐によって命を得なさい」。
私たちも、いざという時にしがみつくべき、イエスの貴重な約束を心して覚えておきましょう。
■一緒に考えてみましょう
・不安な時、恐れ戸惑う時、どんな神様の約束や聖書の出来事を思い出しますか。分かち合ってみましょう。
説教者:藤原 導夫 牧師
聖 書:ローマ人への手紙12章15節
共に喜び、共に泣く
喜んでいる者たちとともに喜び、泣いている者たちとともに泣きなさい。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 20章41節 – 21章4節
価値観の点検
46 「律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場であいさつされることや会堂の上席、宴会の上座を好みます。
47また、やもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちは、より厳しい罰を受けるのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 「キリスト」に期待することのズレ
人々が期待する「キリスト」は、ダビデ王のように外国の支配から解放してくれ人でしたが、
神の約束した「キリスト」はダビデの主であり、ダビデよりさらに偉大な存在でした。
詩篇110篇でダビデがキリストを指して「私の主」と呼んでいることからイエスは「キリスト」の偉大さを語ります。
詩篇110はイエスが復活し、神の右の座に着くことの預言でもあります。
人は神の御心を十分に理解できないので、自分の期待は神の期待とずれていないかどうか、繰り返し、立ち返ることが大切なのです。
- 律法学者に用心するとは
46節の「用心しなさい」とは、「用心し続けなさい」「いつも用心していなさい」というニュアンスです。
律法学者たちは注目されたかったのです。聖書の専門家でしたが、彼らが大切にしていることは、神様の願いとは違うのです。
反面教師にしなければいけません。私たちは油断すると、すぐに神のなさろうとしていることから離れて、迷子になり、
迷子になっていることにも気づかないでいるのです。
私たちはどんなことに価値を置いているでしょうか。神の価値観に照らして、神の愛とあわれみのうちに、点検しましょう。
- 2レプタに目を留めるイエス
レプタ銅貨とは、当時、一番価値の低いお金です。1デナリの132分の1の価値だと言われますので、イメージとしては1レプタ100円くらい。
お金持ちがたくさん献金している中で、貧しいやもめは200円を献げました。
イエス様はこの200円ほどの2レプタに目を留めます。これが私たちの神様です。
用心するようにと言われた律法学者の振る舞いとは反対です。
目立たないですが、イエス様は小さな捧げものに目を留めてくださいます。
■一緒に考えてみましょう
・私たちの期待をはるかに上回る神の偉大さに目を向けることができますように。
・小さな捧げものにイエス様が目を向けてくださるとしたら、私たちは今日、何に注意を向けたらいいでしょうか。
クリスマス
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 20章20-26節
神のものを神に返す
24 「デナリ銀貨をわたしに見せなさい。だれの肖像と銘がありますか。」彼らは、「カエサルのです」と言った。
25 すると、イエスは彼らに言われた。「では、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 「税金」に関する悪巧み
イエスを罠にかけようとしたユダヤ人指導者の回し者たち。ローマ皇帝に税金を払うことは律法にかなっているかと問いかけます。
イエスは悪巧みを見抜き、答えます。カエサルの肖像なら、カエサルに返したらいい。
(つまり、税金を納めたらいい。)ただし、イエスはもう一言付け加えます。
税金の問題もとても大切ですが、より人生の本質に関わることをイエスは語ります。「神のものは神に返しなさい」
- あなたは誰の「肖像(かたち)」か?
デナリ銀貨は、誰の肖像がありますか?カエサルのです。だったら、カエサルに返しなさい。
ここで、私たちは「肖像」という言葉は「神のかたち」と同じ言葉だという知識があると、人は誰の「肖像」もしくは「かたち」ですか?
人は誰の「かたち」に創造されたのですか?というイエスの問いかけが聞こえてきます。
聖書は、人は神ご自身のかたちに創造されたと答えます。
つまり、神のものは神に返しなさいという言葉は、神の「肖像(かたち)」に創造された私たち自身に関することだということに気づくでしょう。
- イエス・キリストこそ「神のかたち」
御子イエス・キリストが生まれ、神のかたちとして生きる人生を示し、十字架で罪責の一切を負われたゆえに、
罪人が赦され神と和解する道が全ての人に開かれました。
パウロは神のかたちに変えられていくクリスチャンの歩みについて、繰り返し語っています。
私たちは古い自分に死に、イエスと共に新たに生きる練習を、毎日している最中です。
でも、この世を照らすまことの光であるイエス・キリストに注意を向け、イエスの栄光を目撃し、イエスの栄光が私たちを作り変えてくださることを、
もっともっと、体験したいのです。
■一緒に考えてみましょう
・どんな時に、神の栄光を目撃したかこの1年間を振り返ってみましょう。神の恵みのうちに神のものを神に返すことができますように。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:マタイの福音書 2章7-8節
小さいという祝福
10 その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。
11 それから家に入り、母マリアとともにいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- いよいよベツレヘムへ
博士たちはベツレヘムという小さな町で生まれるという情報を手にして、再び出かけます。エルサレムからベツレヘムまでは南に9キロほど。
数時間で着きます。とても小さな町だというので、どんな救い主なのだろうと戸惑いながら、その道のりを進み始めたかもしれません。
王宮で、何不自由なく育っている王子様ではないことは確かです。博士たちが最初にイメージした救い主とは違うでしょう。
- あの星の出現
彼らの心配や不安を吹き飛ばしてくれる、星の出現でした。博士たちは星の専門家であり、その星を見たから、ここまで出かけてきたのです。
その星が現れて、導いてくれたとしたら、どれほど彼らにとっては安心したことでしょうか。この道で大丈夫だと思えたでしょう。
聖書をよく知っている人たちは、この記録を読んで、モーセの時代に、雲の柱、火の柱によって、イスラエル民族がエジプトから約束の地まで導かれたことを思い起こしただろうと言われます。不安な道のりも、神が共にいてくれたら、安心できるのです。
- 旅を通して練られた信仰
ベツレヘムで質素な暮らしをしている幼子の家族。博士たちは期待外れとも思わず、ひれ伏して、礼拝したのです。
クリスチャンとは言われない星を読む外国の博士たちですが、博士たちは星を見て、イエス・キリストのお祝いに行く決断をしました。
できる、できないとは関係なく、私たちは神の夢を見せてもらうことがあります。
そして、神の夢は途方もないように見えても、私たちを突き動かし、東の国から博士たちがベツレヘムまでたどり着いたように、実現していくのです。
■一緒に考えてみましょう
・予定通りに行かないという経験を通して、神との関係が深まるということもあります。この1年を振り返って、どんな信仰の旅を歩いてきたでしょうか。
・今の私は、何をイエス様のために贈り物を献げることができるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:マタイの福音書 2章7-8節
小さいという祝福
7 そこでヘロデは博士たちをひそかに呼んで、彼らから、星が現れた時期について詳しく聞いた。
8 そして、「行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから」と言って、彼らをベツレヘムに送り出した。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ヘロデによる虐殺
ヘロデは博士たちを「密かに」呼んだとあります。理由は、博士たちから、星が現れた時期について詳しく聞くためです。
つまり、その子が生まれた時期はいつ頃なのかと彼は計算したかったのです。
その後、博士たちが報告に戻らないことに気づいたヘロデは、聞き出した情報をもとに、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにさせました。
ヘロデの悪事はコソコソとではありません。とんでもない命令が現実に実行されたのです。
- 暗闇の中を生きる救い主
救い主は歓迎されず、命が狙われ、どうにか逃げ延びる。しかし、幼い子供たちは犠牲になってしまいました。
罪に満ちた世界の現実です。イエスが生まれるのは、この暗闇の中なのです。幼いイエスは夜のうちに出発をし、何とか助け出されますが、
エジプトという馴染みのない外国での難民生活が待っています。幼児は虐殺されます。
もっと平和な時代に生まれてきてほしかったと親は思うかもしれません。
しかし、この暗闇の中に、救い主は生まれ、暗闇の中を生きるのです。
- エレミヤの預言がどう重なるか
預言者の語られたことが成就するというのは、前から子供が殺されると定められていたというよりも、
過去の悲惨な記憶と共に、復興してきた国の歩みを思い起こさせるものでした。痛み、悲しみの中に生まれてきた、救い主イエス様。
この世界は今も、トラブル、緊張、暴力、恐怖に満ちています。そうだとしても、どれだけ悲惨な現実でも、イエスは私たちと共にいてくださる。
あなたと一緒にいると言われるのがイエス・キリスト。私たちの救い主。暗闇を照らす真の光です。
■一緒に考えてみましょう
・「悪事はコソコソと」という言葉から、どんな記憶が思い出されるでしょうか。
・暗闇の記憶の中、神はいないと嘆く記憶の中に、イエスを見つけることができるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:マタイの福音書 2章3-6節
小さいという祝福
6 『ユダの地、ベツレヘムよ、 あなたはユダを治める者たちの中で 決して一番小さくはない。
あなたから治める者が出て、 わたしの民イスラエルを牧するからである。』」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ヘロデの動揺
聖書では、東の国から旅してきた博士たちの言葉を聞いて、ヘロデ王は動揺したと記されています。
おそらくこの時期、すでにヘロデは重たい病気だっただろうと聖書外の資料から推測できます。
ちなみにヘロデ王は死ぬ間際まで、後継者を誰にするか迷い、死ぬ5日前にも1人の息子を殺し、後継者を別の息子にしたという記録もあります。
彼は必要とあれば、自分の身内であっても何人も殺していたので、
もし、自分の知らない間に「ユダヤ人の王」として生まれた幼子がいるとしたら、どうしたでしょうか。
- 救い主が生まれる町の特徴
東の博士たちがユダヤの王が生まれたと気づいて、どこに行ったでしょうか。エルサレムでした。
常識的な判断でしょう。神殿があり、信仰の中心であり、政治の中心です。
しかし、ベツレヘムから救い主が生まれるというのが聖書の約束でした。ここに聖書の物事の見方が反映されています。
「小さい」という祝福です。小さな町、取るに足らない町、誰も注目しない町がイエスの誕生の舞台に神によって選ばれるのです。
- 受肉の神秘と小ささ
小ささを喜ばれるというのは、まさにイエス・キリストの生き方そのものだということを思い起こしたいと思います。
クリスマス、人となり、赤ちゃんとなってこの世界に生まれ、無防備になったイエス・キリストを想像したいのです。
ピリピ2:6-11を開いて読んでください。イエスご自身が神としてのあり方にしがみつかず、人となり、仕える者となり、
十字架の死にまで従われたことが記されています。
小ささを認め、神に従う人生は、神によって高く上げられ、父なる神の栄光を表すことをクリスマスを前に思い出しましょう。
■一緒に考えてみましょう
・神様によって「小ささ」が祝福される例を探して、分かち合いましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:マタイの福音書 2章1-2節
旅する東の国の博士たち
1 イエスがヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやって来て、こう言った。
2 「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 思いがけない異邦人の登場
マタイの福音書は聖書を信じるユダヤ人に向けて書かれていますが、2章で出てくるのは東の方からやってきた博士たち。
ユダヤ人から見たら、外国人(異邦人)。「異邦人は神の祝福の外に置かれている」というイメージが当時のユダヤ人にはありました。
しかし、異邦人がユダヤ人の王として生まれた方を探して旅をして来たのです。今のように外国に旅行に行くのは簡単なことではありません。
危険を冒してまで、なぜ、ユダヤ人の王を探しているのか。彼らは礼拝するために来ましたと告白します。
- 誰がイエスを礼拝するでしょうか
本家本元のユダヤ人たちは気づかない間に、ユダヤの王が生まれていました。
それだけでも驚きですが、その知らせをヘロデ王に告げたのは外国の博士たちでした。
本来なら、ユダヤ人が誰よりも、待ち望んでいた救い主の誕生の知らせのはずでした。
しかし、彼らの関心は神には向いていなかったことが今後、明らかになっていきます。
もっと言えば、マタイの福音書全体を読んでも、そのトーンは変わりません。真剣に聞くのは、わずかな人だけです。
- アドベントこそ、立ち止まろう
クリスマスのお祝いのために、忙しいかもしれません。12月の礼拝では、意図的に、立ち止まる時間を持ちたいと思います。
主よ、来てくださいと、イエスを迎える準備をしましょう。イエスが生まれたことに関心が向かないユダヤ人は私たちの鏡です。
他のことに私たちの心は向いているかもしれません。主にもう一度、目を向けましょう。
リスクを冒して旅をしてきた博士たちはクリスチャンではありませんが、彼らも私たちの鏡です。全世界の王を私たちも礼拝しに行きましょう。
■一緒に考えてみましょう
・クリスマスを迎える準備の時期、私たちはどのように過ごそうとしているでしょうか。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 20章9-19節
すれ違いでは済まされない
17 イエスは彼らを見つめて言われた。「では、
『家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった』
と書いてあるのは、どういうことなのですか。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ぶどう園の主人に借りていた農夫
収穫の時が来たので、主人はしもべを、農夫たちのところに遣わします。
主人の代わりに来たしもべを3回も打ち叩き、何も帰らせたというのは、神様が繰り返しイスラエルに遣わした預言者たちへの態度が思い出されます。
最後には、主人のぶどう園を自分たちのものにしようとして、なんと息子を殺してしまうのです。
ぶどう園を奪おうとした農夫は殺され、他の人たちが管理することになります。なんというたとえ話でしょうか。
- 家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった
詩篇118:22の引用。ユダヤの指導者たちが捨てた石がイエス・キリストです。役に立たない、邪魔な石でしたが、要の石となる。
一度は捨てられたが、神は捨てられた石を最も重要な要の石として用いる。これが聖書の約束です。
これが聖書の大逆転です。死がいのちとなる。死を通して、命を与える。
この詩篇の一節は新約聖書の中で何度も繰り返し引用され、イエス・キリストの十字架の死と復活の、神の神秘を解き明かす言葉として用いられます。
- そんなことが起こってはなりません
16節の民の反応です。元々この話は人々に向けて語られたのです。
農夫の側に立ちながら、聞こうとした人はいたでしょうか。私たちも農夫なのです。神に託されたものに忠実でしょうか。
聞き慣れない神の声を聞いているでしょうか。誰も完璧な人はいません。どこにも完全な教会はありません。
でこぼこがいいと言ってくださるのは、ただただ、神の恵みによるのです。
律法学者たちと祭司長たちは、このたとえ話が自分たちを指して語られたことに気づいた。
私たちも気づき、立ち止まり、何をしたらいいでしょう。
■一緒に考えてみましょう
・神に託されていることに忠実でしょうか。預言者の声、神の聞き慣れない声を聞こうと立ち止まっているでしょうか。
・「捨てた石が、要の石となる」という神の神秘について祈ってみましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 19章47-20章8節
権力者に脅されたら
20:1 ある日、イエスが宮で人々を教え、福音を宣べ伝えておられると、祭司長たちと律法学者たちが長老たちと一緒にやって来て、
2 イエスに言った。「何の権威によって、これらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのはだれなのか、教えてくれませんか。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 誰を見ながら生きているか
当時、どのようにして祭司たちのトップである大祭司が決められていたでしょうか。
ヘロデ大王の時代、世襲制だった大祭司をヘロデが解任し、自分で大祭司を選ぶようになり、
ローマ支配下でも、同じようにローマ側が大祭司を選んでいました。そもそも祭司とは、神の民を代表し、神との間に立つ役割でした。
残念ながら、当時の大祭司は誰の目を気にして仕事をしていたかというと、聖書の神ではなく、ローマ総督を見ていたのです。
- 神殿の権威が揺さぶられていた
バプテスマのヨハネをどうして大祭司たちは認めなかったのでしょうか。
理由の一つは、バプテスマのヨハネは神殿を無視したからだと言われます。悔い改めるためには、神殿で犠牲を捧げるのが聖書の常識でした。
ですが、バプテスマのヨハネは神殿ではなく、ヨルダン川で、罪の赦しを受けるために悔い改めのバプテスマを受けなさいと語りました。
聖書には形だけのいけにえより、真心を持って主に仕えることが大切だと預言者は繰り返し警告していたのですが、
神への冒涜とある人たちには映ったことでしょう。
- 神の権威はイエスから教会へ
イエスは神から権威を託されていました。この権威がイエスの弟子たちに、キリストを頭とする教会に託されています。
私たちはこの権威を適切に使っているでしょうか。神に託された使命に生きているでしょうか。
私たちは誰を見ながら、誰の目を気にして、暮らしているでしょうか。
「神様、罪人の私をあわれんでください」と祈った取税人のように、私たちは正直に、不完全なままで、
でこぼこなままで、神の前に祈りを捧げたいと思います。弱さのうちに主の栄光は表されるのです。
■小グループで分かち合うヒント
・私たちは誰の目を気にしながら暮らしているでしょうか。
・神の霊はどのように今の私たちを刷新しようとしているでしょうか。神の導きに開かれた心でいるために、どのようにしたらいいでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 19章28-46節
祈りの家か強盗の巣か
46 彼らに言われた。「『わたしの家は祈りの家でなければならない』と書いてある。それなのに、おまえたちはそれを『強盗の巣』にした。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- イエスの示す王らしさ
ベタニアという町に着きました。エルサレムまでは残り3キロほど。もう目的地は目の前です。ここでイエスは動物に乗ります。
どんな動物か。それは子ろばです。旧約聖書ゼカリヤ書9:9に王が来るときの約束が記されています。
そこに、ろばに乗って来ると書いてあります。軍事力を象徴する白馬ではなく、ロバに乗り、平和と謙遜さ、もしくは低さを表します。
これこそ、主が必要とされていることでした。さて、私たちは、どんな王を求めているでしょうか。
- 喜んで賛美していますか
「祝福あれ、 主の御名によって来られる方、王に。」(19:38) 大勢の弟子たちの賛美は、詩篇118篇から取ったものです。王を迎える賛美です。
イエスを王として、救い主キリストとして、エルサレムに迎えようとしているのです。イエスと旅をしてきた私たちは、自分自身に問いかけたいと思います。イエスとの旅で、何を見てきたでしょうか。神の力ある働きを目撃し、喜んでいるでしょうか。
神の国の福音、神の恵みの福音を目撃し、私たちは神の風に吹かれて、大声で歌う準備ができているでしょうか。
- 神の家が滅んだ過去
神殿は、神の家でした。神の家は、あらゆる民の祈りの家(イザヤ56:7)として開かれているべき場所でした。
しかし、実際はあらゆる民に開かれてはいませんでした。また、神殿が滅ぼされるとは誰も想像もしませんでした。
しかし、旧約聖書の時代、預言者エレミヤは警告しました。
「わたしの名がつけられているこの家は、あなたがたの目に強盗の巣と見えたのか。見よ、このわたしもそう見ていた──主のことば──。」(エレミヤ7:11)
祈りの家が強盗の巣に。悪い冗談のようですが、神からの本気の警告です。
■一緒に考えてみましょう
・私たちは何を願っているでしょうか。白馬の王様と子ロバに乗ったへりくだった王様、どちらでしょうか。
・神様は思わぬ姿で訪問されます。私たちは迎える準備ができているでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 18章31-43節
神のギフトはあなたにも
17 主人は彼に言った。『よくやった。良いしもべだ。おまえはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。』
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 次回、エルサレムに入ります
イエスが王としてエルサレムに到着する。いよいよ待ち望んでいた瞬間がやってくる。
そういう期待の中でこれから何が起こるかを告げようとしている気がします。
預言的でありつつも、預言者が常に神に立ち返りなさい、神のところに戻って来なさいと告げるように、
イエスもきっと、今からでも戻ってきなさいと言いたいのかもしれません。でも、なかなかその思いは人々に届きません。
- 使命を忘れ、何もしない
商売しなさいと言われたのに、何もしなかった人がいました。
また、イエスが王となるのを望まず反対した人たちの運命はもっと過激です。王の目の前で殺されます。
残酷に見えるかもしれませんが、当時の常識として受け止められたらと思います。
約束の救い主が戻ってくるまでに、「ちゃんと準備しておきなさい」と旧約聖書の預言者たちは何度も警告しました。
しかし、主人がいない間、命令を忘れ、何もしないで主人を迎えることになるしもべがいるのです。
- やってみようの精神も大事
主人の言葉を忘れずに、100万円ほど託され、10倍にした人、5倍にした人がいます。
誰もが神からギフトを託されています。王がいないとき、言われた言葉を忘れずに自分の使命を全うしたいと思います。
すでに神は何かを始めています。私たちの周りで、何かが始まっています。
神の国はからし種のように小さいかもしれませんが、神が確かにそこにいて育てていきます。
1ミナは手元にあります。失敗するリスクはつきものですが、商売しなさいと主人は言われるのです。
ほんの小さなことに忠実でいることができますように。
■一緒に考えてみましょう
・私の手元にある1ミナを神のために使うとは、どういうことでしょうか。私の周りで神は何かをすでに始めているとしたら、それは何でしょうか。
ルカの福音書講解
説教者:川口竜太郎 師 hi-b.a.代表スタッフ
聖 書:イザヤ書43章 1-4節
あなたの神
1 だが今、主はこう言われる。
ヤコブよ、あなたを創造した方、
イスラエルよ、あなたを形造った方が。
「恐れるな。わたしがあなたを贖ったからだ。
わたしはあなたの名を呼んだ。
あなたは、わたしのもの。
2 あなたが水の中を過ぎるときも、
わたしは、あなたとともにいる。
川を渡るときも、あなたは押し流されず、
火の中を歩いても、あなたは焼かれず、
炎はあなたに燃えつかない。
3 わたしはあなたの神、主、
イスラエルの聖なる者、
あなたの救い主であるからだ。
わたしはエジプトをあなたの身代金とし、
クシュとセバをあなたの代わりとする。
4 わたしの目には、あなたは高価で尊い。
わたしはあなたを愛している。
だから、わたしは人をあなたの代わりにし、
国民をあなたのいのちの代わりにする
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 19章1-10節
神はあなたを探している
9 イエスは彼に言われた。「今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。
10 人の子は、失われた者を捜して救うために来たのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ザアカイを照らした光
ザアカイのもてなしを受けたいと思う人など、誰もいなかったのです。ザアカイはお金を持っていましたが、彼もまた社会から弾き出されていたのです。
彼もまた本当の孤独を知っていた人でした。神から見放され、人から見放される辛さを知っていました。
イエスが語った「あなたの家に泊まる」という言葉は、ザアカイの暗闇を照らす光になりました。
神の愛に照らされ、包まれた瞬間でした。
- 文句を言う群衆
神が1人の人を救おうとしているその瞬間、周りの人は喜ばずに文句を言うのです。
この反応はリアルだなと思います。私たちはあの人が罪人だということをよく知っているので、神の判断が受け入れられないのです。
今回はあのザアカイ。ただの罪人ではありません。罪人の中の罪人。神様から一番遠くにいる人なのです。
イエスはもちろんザアカイを知っています。どれほど深い闇の中にいるかを、そして、光を待ち望んでいることを。
- 恵みが先に与えられる
「恵みが私たちに与えられるのは、私たちが善い行いをしたからではなく、私たちが善い行いをすることができるようになるためである」アウグスティヌス
じっくり味わいたいなと思います。本物の恵みに触れるなら、私たちは変わっていきます。
ザアカイを変えたように、今日私たちを変えていくのは神の恵み、神の愛なのです。
金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が簡単だとイエスは言いましたが、人にはできないことが神にはできるとも言われました。
ラクダが針の穴を通ることもある。これが今日のストーリーです。
■一緒に考えてみましょう
・もし、イエスの弟子の1人としてこの場にいたら、あなたは誰の側に立ちながら、この出来事を目撃することになるでしょうか。
・そんなあなたに神様はどのような声をかけようとされると思いますか。
説教者:広瀬 由佳 師
聖 書:ヨハネの福音書3章1-21節
光と風の物語
1 さて、パリサイ人の一人で、ニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。
2 この人が、夜、イエスのもとに来て言った。「先生。私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。
神がともにおられなければ、あなたがなさっているこのようなしるしは、だれも行うことができません。」
3 イエスは答えられた。「まことに、まことに、あなたに言います。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」
4 ニコデモはイエスに言った。「人は、老いていながら、どうやって生まれることができますか。
もう一度、母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。」
5 イエスは答えられた。「まことに、まことに、あなたに言います。人は、水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。
6 肉によって生まれた者は肉です。御霊によって生まれた者は霊です。
7 あなたがたは新しく生まれなければならない、とわたしが言ったことを不思議に思ってはなりません。
8 風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。
御霊によって生まれた者もみな、それと同じです。」
9 ニコデモは答えた。「どうして、そのようなことがあり得るでしょうか。」
10 イエスは答えられた。「あなたはイスラエルの教師なのに、そのことが分からないのですか。
11 まことに、まことに、あなたに言います。
わたしたちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなたがたはわたしたちの証しを受け入れません。
12 わたしはあなたがたに地上のことを話しましたが、あなたがたは信じません。それなら、天上のことを話して、どうして信じるでしょうか。
13 だれも天に上った者はいません。しかし、天から下って来た者、人の子は別です。
14 モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられなければなりません。
15 それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」
16 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。
それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。
17 神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである。
18 御子を信じる者はさばかれない。信じない者はすでにさばかれている。神のひとり子の名を信じなかったからである。
19 そのさばきとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。
20 悪を行う者はみな、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。
21 しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
説教者:関野 祐 先生
聖 書:ヨハネの福音書18章1-11節
低さの極みで栄光を受ける主
1 これらのことを話してから、イエスは弟子たちとともに、キデロンの谷の向こうに出て行かれた。
そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。
2 一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちと、たびたびそこに集まっておられたからである。
3 それでユダは、一隊の兵士と、祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりとたいまつと武器を持って、そこにやって来た。
4 イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て、「だれを捜しているのか」と彼らに言われた。
5 彼らは「ナザレ人イエスを」と答えた。イエスは彼らに「わたしがそれだ」と言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。
6 イエスが彼らに「わたしがそれだ」と言われたとき、彼らは後ずさりし、地に倒れた。
7 イエスがもう一度、「だれを捜しているのか」と問われると、彼らは「ナザレ人イエスを」と言った。
8 イエスは答えられた。「わたしがそれだ、と言ったではないか。わたしを捜しているのなら、この人たちは去らせなさい。」
9 これは、「あなたが下さった者たちのうち、わたしは一人も失わなかった」と、イエスが言われたことばが成就するためであった。
10 シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。
11 イエスはペテロに言われた。「剣をさやに収めなさい。父がわたしに下さった杯を飲まずにいられるだろうか。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 18章31-43節
何をしてほしいのか
40 イエスは立ち止まって、彼を連れて来るように命じられた。彼が近くに来ると、イエスはお尋ねになった。
41 「わたしに何をしてほしいのですか。」するとその人は答えた。「主よ、目が見えるようにしてください。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 隠されていること
時に私たちの不信仰によって、見えなくなることもありますし、神によって隠されることもあります。これを神の神秘と呼びます。
先週、人にはできないことが神にはできるのですとイエスは言いました。弟子たちはエルサレムに向かっていることは知っています。
でも、そこで何が待ち構えているか、聞いていても、理解はできませんでした。時があるのです。
隠される時があり、明らかにされる時があります。やがて、復活の主にお会いして、弟子たちは目が開かれます。
- あわれんでくださいという祈り
「ダビデの子」というのは大切な信仰の告白です。ダビデの子という言葉には、聖書が約束した、やがて来られる救い主という響きがあります。
救い主をギリシャ語訳はキリスト。この盲人はイエスのことを、聖書が約束した救い主キリストであると大声で告白したのです。
「私をあわれんでください」という祈り、ちょっと前に出てきました。取税人の祈りです。
『神様、罪人の私をあわれんでください。』さらに、18章のやもめのように、あきらめずに求め続ける姿も重なります。
- 求めるべきことを求めていますか
イエスは歩くのをやめ、立ち止まり「私に何をしてほしいのですか」と問うのです。
当時、神ならツァラアトを清めることができる。しかし盲目は癒されることがないと広く信じられていたということは大事なことかもしれません。
「今日、食べる物がないのです」「もうお金がないのです」と言うでしょうか。盲人は「目が見えるようにしてください」と頼みます。
私たちはどれくらいイエスに期待しているでしょうか。一番、祈らなければいけないことに自分で気づいているでしょうか。
■一緒に考えてみましょう
・一番、祈らなければいけないことに自分で気づいているでしょうか。
案外、私たちは周辺のことは祈っても、中心のことを祈らないことがあり得ます。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 18章18-30節
人にできないことが神には
26 それを聞いた人々は言った。「それでは、だれが救われることができるでしょう。」
27 イエスは言われた。「人にはできないことが、神にはできるのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 人間の基準は神とは違う
「私は少年のころから、それらすべてを守ってきました」と告白する指導者は、先週出てきたパリサイ人と同じタイプです。
自分やちゃんとしている。よくやっている。努力してきた。周りもそう認めているし、自分も心から信じていました。
自分で自分を正しいと思い、真っ直ぐに生きていると思うタイプの人ですが、「何をしたらいいか」という最初の質問からズレていました。
何かをすることで、神の子どもに値すると認められることは事実上、不可能です。
- 神よりも大切な「何か」
この指導者はお金を手放すことには、大きな抵抗がありました。イエスは私たちの深い部分に触れられます。
魂に触れると言ってもいいかもしれません。
私たちは「心を尽くし、いのちを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」という最も基本的な命令にも十分に応じることができません。
むしろ、心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして愛してくれるのは神様の側ではないでしょうか。
神に近づけば近づくほど、神の大きさと自分の小ささに気づくものです。
- 手放すことも恵みによって
自分の富をキリストの足もとに置く覚悟はあるでしょうか。
私たちはお金ではなくても、自分の大切にしているものをイエス・キリストの足元に置き、手放す覚悟はあるでしょうか。
もう少し、丁寧に語るなら、神は最も大切なひとり子、イエス・キリストを手放すほどに私たちを愛しています。
神の愛が信頼に足ると体験するほど、私たちは自分の大切なものを神の前に手放すことができるようになるだろうなと思います。
覚悟というと、自分の決断のような感じがするかもしれませんが、手放す信仰もまた神の恵みから始まります。
■一緒に考えてみましょう
・この指導者にお金を手放すようにとイエスは促したとしたら、私には何を手放すようにとチャレンジをされるでしょうか。
じっくり考えてみたり、親しい人に聞いてみたりして、自分の盲点に光を当ててみましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 18章9-17節
高慢になるリスク
9 自分は正しいと確信していて、ほかの人々を見下している人たちに、イエスはこのようなたとえを話された。
10 「二人の人が祈るために宮に上って行った。一人はパリサイ人で、もう一人は取税人であった。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 「自分は正しい」という錯覚
パリサイ人もイエスの弟子たちも、神の恵みの邪魔をしているのに気づかないだけでなく、
自分は正しいことをしていると錯覚しているという共通点があります。
パリサイ人は自分で決めたルールを守っていることで信仰深いと勘違いをし、取税人を心の中で裁きます。
イエスの弟子たちは当時の価値観に影響され、幼い子どもたちを価値のない存在と見なし、イエスから引き離そうとしました。
イエスは何がずれているのか、明らかにしてくださいます。
- 神に全面的に頼る生き方
取税人のように、自分の罪を認め、神に心からの助けを求める人を神は憐れむとイエスは教え、
数にも数えられないような幼い子どもたちから信仰の本質を学ぶようにと弟子たちに語りました。
小さな子どもは本能的に、頼るということを知っています。小さな子どもが全面的に頼るように、
私たちも全面的に神に頼ることを学ばなければ、神の王国、神がここですでに働いていることを見つけることはできないのです。
全ての人は罪人で、神の恵みによって救われるという信仰の本質に立ち返るようにとこの出来事は語りかけています。
- 失敗に気づくことから
失敗は少ない方がいいと思うかもしれませんが、自分では気づいていないだけで、
私たちは失敗ばかりと言ったほうが現実を的確に表現しているかもしれません。
大切なのは失敗に気づくことです。失敗に気づかないまま「私は正しいことをしている」と思っていたら、
いつまでも神様は必要ありません。失敗したら、恥ずかしいと思うかもしれませんが、
隠し続けていても、何も変わりません。失敗を神の光の中に差し出すことが、あわれんでくださいという祈りです。
■一緒に考えてみましょう
・失敗に気づかないまま「私は正しいことをしている」と思っていたら、いつまでも神様は必要ないでしょう。
今日、神の優しい光の中で何に注意を向けたらいいでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 18章1-8節
粘り強い祈りが世界を変える
1 いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちにたとえを話された。
2「ある町に、神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。
3その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやって来ては、『私を訴える人をさばいて、私を守ってください』と言っていた。
4この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。『私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、
5このやもめは、うるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。
そうでないと、ひっきりなしにやって来て、私は疲れ果ててしまう。』」
6主は言われた。「不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。
7まして神は、昼も夜も神に叫び求めている、選ばれた者たちのためにさばきを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。
8 あなたがたに言いますが、神は彼らのため、速やかにさばきを行ってくださいます。
だが、人の子が来るとき、はたして地上に信仰が見られるでしょうか。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 訴えを聞いてくれない裁判官
イエスは神を愛することと人を愛することが大切だと教えました。イエスのたとえに出てくるこの裁判官は聖書の価値観とは反対です。
「神を恐れず、人を人とも思わない」と書いてあります。神様が旧約聖書の中で、特別に守ろうとする3つの立場の人たちがいます。
やもめとみなしごと在留異国人ですが、この裁判官は、神も人も大切にしないので、やもめだから、助けてあげようとは全く考えないようです。
実際、やもめの訴えを彼は聞こうとしません。
- それでも訴え続ける女性
この女性は裁判官に訴え続けました。ひっきりなしにやって来てと書いてあるように、彼女は何度も何度もやって来ました。
社会的な後ろ盾もない彼女に残された武器は、粘り強さ・あきらめない心だけでした。
何度も嫌な思いをしたでしょうし、失望しそうになったことでしょう。実際に、落胆し、落ち込んだ日もあったでしょう。
でも、彼女は粘り続け、最後にはあのひどい裁判官が動いたのだとしたら、
愛と正義を兼ね備えた神に対して、粘り強く頼む人がいるなら、確かに神は行動してくださるに違いありません。
- 粘り強い祈りは主に届く
神様は私たちを見ています。私たちの忍耐を見ています。イエス様が私たちの期待するタイミングで来ないことがあります。
それでも、諦めてはいけません。「主よ、来てください」と教会は祈り続けて来ました。粘り強い祈りが私たちに求められています。
大きな、派手な信仰は必要ありません。からし種のような小さな信仰で十分です。小さな信仰で、粘り強く祈りましょう。
この小さな信仰を通してゆっくり、でも確かに神の王国はこの世界に表されるのです。
■一緒に考えてみましょう
・祈りの答えがほしくて私たちはせっかちになるかもしれませんが、どのようにして忍耐強く失望せずに祈り続けることができるでしょうか。
・諦めそうになっている祈りがあるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 17章20-37節
神の愛が見えますか
20 パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。「神の国は、目に見える形で来るものではありません。
21 『見よ、ここだ』とか、『あそこだ』とか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなたがたのただ中にあるのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- イエスが使った宣教の合言葉「神の王国」
ルカ4:43で「ほかの町々にも、神の国の福音を宣べ伝えなければなりません。
わたしは、そのために遣わされたのですから」とイエスは語りました。
イエスが伝えたかった福音、それは「神の国」に関することだと言われます。
イエスは「神の国」という言葉を「神が王として支配する」という意味で使いました。
イエスの宣教というのは、今まさにイエスご自身が王として行動し、神の王国を、今ここで、実現しているということを示したのです。
神の国をからし種にたとえたように、小さなことが次第に大きくなっているプロセスでもあります。
- イエスが見えず、苦しい経験をしても
イエスは「人の子の日を見られない日が来る」と言いました。イエスの弟子として歩く決心をしたけど、イエスが見えない・祈っても助けが来ない気がする。そういう真っ暗な夜のような時期をクリスチャンは経験すると語りました。聞こえのいい言葉にすがりたくなるかもしれません。
ですが、追いかけてはいけません。苦難の中でも、イエスが見えないと思っても、神の愛は私たちから決して離れませんから、
私たちも神様に忠実でいることができますように。
- 終わりの時は恐怖を煽るためではない
終わりの時に関する聖書の伝えたいメッセージは、恐怖を煽ることではありません。
終わりの時は「いつか」は分からないから、今日も神と共に誠実に忠実に心を込めて生活しましょう。
やがて悪は裁かれ、苦しみから救われます。ツァラアトのようにあの人はここにいてはいけない、共同体の外に行けと誰も言われないように。
神の憐れみに頼り、お互いを迎えることができますように。まず人の子が苦しみ、教会も苦難の時代を通り、栄光へと至るのです。
■一緒に考えてみましょう
・「今、ここ」に目を向けたら、「神の王国」(イエスが王、キリスト、救い主として行動している)を見つけることができるでしょうか。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 17章11-19節
感謝する人、しない人
17 すると、イエスは言われた。「十人きよめられたのではなかったか。九人はどこにいるのか。
18 この他国人のほかに、神をあがめるために戻って来た者はいなかったのか。」
19 それからイエスはその人に言われた。「立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- ツァラアトという呪い
ツァラアトが見つかったら「汚れている」と叫び、共同体の外に出ていかなければなりませんでした。
ツァラアトの治療方法はありません。元に戻せるとしたら、神の奇跡だけです。
イエスがツァラアトの人をきよめたという情報が彼らの耳にも届いていたことでしょう。
イエスがこの村に来てくれたので、必死に彼らは「あわれんでください」と叫びました。
「あわれんでください」とは神に対する祈りの中で使われる言葉です。イエスを救い主として信仰を告白しているのと同じことです。
- イエスの言葉を信じ、従った人たち
もしかしたら、聞いていた情報を違うと思ったかもしれません。
以前は「私の心だ、きよくなれ」とツァラアトの人に直接、触れて、癒されました。
なのに、今回は「行って、自分のからだを祭司に見せなさい」と言われただけでした。
彼らはイエスの言葉を信頼し、祭司のところに向かい、その途中できよめられたことに気づきます。
イエスを信じ、従った彼らの信仰が奇跡を実現させたのです。
このあと、イエスのところに感謝を伝えに来たのは1人のサマリア人だけでした。
- 本質を見誤らないように
イエスが使った「他国人」という言葉は、エルサレム神殿で正式に使われている言葉でした。
他国人はここまでしか入ってはいけませんというエリアが決められていました。
一番遠くで我慢させられるのが他国人、次は女性のエリア、最も近づけるのは男性という括りが神殿で礼拝する時に存在していました。
そのエリアを守れなかったら殺されてしまうほど、厳しい決まりでした。
イエスには意味のない区別でした。生まれではなく信仰が本質なのです。
■一緒に考えてみましょう
・神からの祝福に対して、感謝をしないままにしていたことはあるでしょうか。
・当時「サマリア人」に対する偏見があったように、私たちはどんな偏見があるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 17章1-10節
「ゆるす」という選択肢
3 あなたがたは、自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして悔い改めるなら、赦しなさい。
4 一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回あなたのところに来て『悔い改めます』と言うなら、赦しなさい。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 赦し、赦される
イエスの弟子たちは、神に赦されていることを知っているので、「あなたが赦されたように、あなたも人を赦しなさい」とはっきりイエスは語ります。
私たちはこの教会のような共同体で体験していくことができます。
ただ、私たちは、1回赦し、2回赦し、段々とストレスや怒りが溜まっていき、もう3回目なんだけど!と我慢の限界に達したりすることがあるでしょう。
それでも、私たちが悔い改め、赦しを与え、赦しを受け取るとき、この世界は神の似姿に一歩、近づいていきます。
- 今ある信仰で十分!
使徒たちは信仰を増し加えてくださいとお願いしました。イエスは小さな信仰があれば、神様の奇跡を目撃できますと言っています。
これは弟子たちへの叱責の言葉ではありません。むしろ、私たちがわずかな信仰、頼りない信仰と自分で思っているかもしれない信仰であっても、
ゼロでないなら、少しだとしてもその信仰でイエスに頼るなら、十分だと言われるのです。
そうすれば、あなたにとって信じられないことが起こると神様が約束してくれているのです。
- なすべきことをしただけです
こういう言葉が口から出てくるような奉仕をさせていただけたらと思います。
これだけのことをした!これだけのお金を捧げた!と主張したくなることがあるかもしれません。
神は「よくやった!忠実なしもべだ!」と評価する場面もあるので、もちろん、見ていてくれるのですが、
今日のポイントは、弟子の生き方です。弟子は神に赦された同じように赦します。
イエス様がしもべとなって私に仕えてくださるから、私も奉仕します。受けた恵みを、次の人に渡していく。
恩着せがましくない。これが神の国での弟子の生き方です。
■一緒に考えてみましょう
・「なすべきことをしただけです」と心から思えた瞬間を振り返ってみましょう。きっとあるはずです。その経験を大切にしたいと思います。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 16章19-31節
無視すべきではなかった人
25 するとアブラハムは言った。
『子よ、思い出しなさい。おまえは生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けた。しかし今は、彼はここで慰められ、おまえは苦しみもだえている。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 死んでから慰めを受ける
葬儀の様子は描かれていませんが、きっとお金持ちは葬式も豪華で、立派なお墓に葬られたことでしょう。
一方で、ラザロは貧しい人たちが入るお墓に入っていたことでしょう。
聞いている人たちの予想に反して、イエスはラザロが天使たちによってアブラハムの懐(祝福の場所の象徴)に運ばれたと言います。
連れて行かれたという言葉には、いるべき場所に戻るというニュアンスが含まれています。
死んだ後、ようやくいるべき場所に戻ることができました。
- 愛の反対は無関心
お金持ちは人生ですべての良いものを受け取ってきましたが、それを当然のことと思い、祝福を分かち合いませんでした。
つまり、自分の託されている財産をラザロと分かち合わず、自分のことだけ考えてき生きていました。
愛の反対は無関心だと言われます。お金持ちからしたら、ラザロのことを憎いとは思わなかったでしょうが、
ラザロに関心を払おうとも思わなかったことでしょう。
私たちは今、愛をもって関心を向けるべき人はいるでしょうか。
- 真剣に神のことばを聞いているか
すでに聖書は警告を与えています。ただし、真剣に耳を傾ける人はあまりに少ないのです。
あとから後悔しても遅いのです。律法・預言者は、表面的な信仰ではなく、神を知ること、愛することを求めます。
神を愛することは、周りの人を愛し、仕えることと結びついています。
私たちは神に委ねられた賜物を神と他者のために使っているでしょうか。
私たちは真剣に神の警告に耳を傾けているでしょうか。
金持ちも、その兄弟も、神のことばを甘く見ていました。私たちは真剣でしょうか。
神は今日も戻ってきなさいと私たちを招き、探してくれます。
■一緒に考えてみましょう
・無視しそうになるけど、無視すべきではない人に目を向ける勇気を与えてくださいと一緒に祈り合いましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 16章14-18節
お金に心を奪われないで
14 金銭を好むパリサイ人たちは、これらすべてを聞いて、イエスをあざ笑っていた。
15 イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、人々の前で自分を正しいとするが、神はあなたがたの心をご存じです。
人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 人の賞賛に心が奪われる
パリサイ派の人たちは、簡単に手に入る、賞賛に満足していました。
それは人々から、あの人はすごい、立派だ、よくできた人だ、と言われるような人からの賞賛の声です。
彼らは、施しと言って、貧しい人たちにお金をあげるという行為を日常的にしていました。行為としては信仰の行為。神様のためにしていそう。
だけど、実際には、神に心は向いていないことがあります。これは、特に預言者たちが警告していますが、神の前では、忌み嫌われるものです。
- 自分の正しさを証明する誘惑
自分で正しい行動をして、自分の正しさを証明したくなる。これは一見、正しいようですが、自分が神になろうとする罪の道です。
神が私たちを探しに来てくれることを今日も思い出しましょう。私たちは自分の力で神の正しさに完全に到達することは不可能です。
ここに気づかないのがパリサイ派に通じる生き方です。私は不完全、むしろ欠けばかりだけど、私を尊いといい、
私のためにイエス・キリストが命を差し出し、全てをくださるのが神の愛です。神の愛ゆえに、
神から「私の子供」と言ってもらうのが聖書が教える救いの道です。
- なぜ離婚の話?
パリサイ人は、合法的に、離婚して、再婚できる抜け道を用意しました。
結婚している男性が他に結婚したい女性を見つけた時に、自分の欲求を実現するための一つの手段が離婚でした。
これがパリサイ人の生き方を象徴しています。神が与えた律法を自分たちの都合の良いように解釈し、周りからは神に従っているように見えるようにし、
自分でも神に従っていると思っている。神の真意を理解しようとせず、自分に都合のいい生き方への警告を受け止めましょう。
■一緒に考えてみましょう
・私の信仰は誰から始まっているでしょうか。探し求める神様からでしょうか。
パリサイ人のように自分の正しさでしょうか。欠けている私たちに恵みを与えるのが聖書の神です。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 16章1-13節
小さなことに忠実に
10 最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 伝統的な解釈
伝統的な解釈では、不正な管理人が、主人の財産を浪費し、首になりそうになり、借りている人たちの好意を得るために借りているものの数を減らして帳簿を改ざんしました。
この場合、不正をしていた管理人の将来に備えた危機対応に抜け目がなかったと誉められたという解釈がなされます。
自分が首になりそうだと分かったら必死になって生き延びる方法を考えたように、
イエスの弟子として永遠に至る道を歩くときに、必死になっているか、という弟子への警告がなされているのです。
- もう一つの解釈
聖書の伝統では、お金を貸してお金儲けをすることは禁じられていました。
法律の抜け道として、ものを貸して、利息を取るということが行われていたそうです。
この管理人がしたのは、利息分を減らして、借りていた人を喜ばせつつ、律法の定めに従った契約に修正することで、主人の名誉を回復させることになった。これが賢いと誉められる理由だという見解です。そうだとしたら、この世のお金を増やすことだけを考えるよりも、
むしろ、困っている人を助けるためにお金を使いなさい。これが永遠へと至る生き方なのです。
- 神に託されたものという価値観
お金の扱い方を具体例に挙げながら、忠実でありなさいと言われます。小さな日常的な事柄をはじめとして、私たちは神への忠実さが問われています。
「管理人」という言葉から、私たちの人生の全ては神に託されたものであるという聖書の視点を思い出したいと思います。
私たちが自分で手に入れたと思うようなことも神から委ねられ、託されたものであり、
それを私たちは不正に管理するのか、忠実に管理できるのかが問われています。
■一緒に考えてみましょう
・神に託されたものに忠実でしょうか。もっと危機感を持って管理しなければならないことについて何か思い当たるでしょうか。
人を助けるために何ができるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 15章11-32節
一緒に喜んでくれますか?
31 父は彼に言った。『子よ、おまえはいつも私と一緒にいる。私のものは全部おまえのものだ。
32 だが、おまえの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。』」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 神の愛が先にあって、悔い改めへ
何がきっかけで我に返ったかは記されていません。ですが、弟息子は少なくておも、お父さんの愛情を知っていました。
お父さんは家族だけでなく、家で働く人にまで大切にする人でした。聖書では、神のところに戻る決意を悔い改めと呼びます。
悔い改めは人間がすべきことだと見なされることがありますが悔い改める前に、神が探してくれるのであり、神の愛が常に先にあるのです。
この神の愛に気づかなければ、本当の意味で、悔い改めることはできません
- 威厳よりも愛情
弟息子のような愚かな息子を持った父親というのは、周囲からの視線が痛かったはずです。
こんな息子が帰ってきたら、お前なんか知らんと言うかもしれないし、ぶん殴ってやらないと気が済まないかもしれませんが、
この父親は駆け寄って、抱きしめるのです。イエスの時代の父親は決して走り回ったりしないものでした。
走らないことが威厳を示すことでした。でも、このお父さんは息子を見つけたら、もうじっとしていられなくて、走って迎えるのです。
- 弟も兄も抱きしめたい父
兄息子は、一見すると父親のために働き、従順で、ちゃんとしている息子だと自分も思っていたと思うし、周りからもそう見られていたかもしれません。
ただ、この息子は自分のことだけ考える傾向にあり、神の愛の本質を理解できませんでした。
弟も兄もでこぼこですが、天のお父さんには大切な存在です。神様の愛は、信じられないくらい広く、深いのです。
放蕩して帰ってきた弟を一緒に喜んでほしいと、近くにいながらも父親の愛に気づいていない兄に問いかけます。
迷子を必死に探す神様は、今日、弟も兄も抱きしめ、一緒に喜びたいのです。
■一緒に考えてみましょう
・今日の私は弟のようでしょうか、兄のようでしょうか。私たちも成長し、父親のように振る舞えますように。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 15章1-10節
迷子を必死に探す神
9 見つけたら、女友だちや近所の女たちを呼び集めて、『一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたから』と言うでしょう。
10 あなたがたに言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 罪人と食事をする理由
取税人というのは、神を嫌っているし、神からも嫌われている人の代表的な職業の人です。
そういう人がイエスに近づこうとすることが驚きですし、イエスがそういう人を拒まずに受け入れて、食事をするということも、
聖書に従おうとするパリサイ人や律法学者たちには、理解できないことでした。罪人と一緒にいたら、自分まで汚れてしまうというのが当時の常識でした。
それなのになぜ、このようなことが起こったのか、イエスはたとえを使って説明します。
- いなくなった1匹の羊を探す
どれほど苦労したか、心配したか、大変だったかよりも、天では、1人の罪人が悔い改めるなら、大きな喜びが湧き上がります。
迷子になった羊の話で強調されているのは、必死に探しに行ったのは羊飼いの側だということです。
羊は自分で戻ってこられません。だから、羊飼いである神様が羊である人間を探しに来てくださるのです。
イエス様は良い羊飼いとして、羊のために、自分の命を捨てる覚悟で、迷子になった羊を探しています。
- 救いの喜びが原動力に
悔い改めるのを待っているのではなく、まず、神が探しに行く。いなくなった羊を探す羊飼いも無くしたお金を探す女性も必死に探しました。
この必死さこそ、失われた人を探し出そうとする神の熱意、情熱です。
それほど、全ての人が神にとっては大切な存在であり、神の愛に触れることによって、人は悔い改めへと進んでいくことができるのです。
イエスが罪人たちと喜んで食事をする理由はこれなのです。
罪人たちは見つけてもらった喜び、イエスは見つけることができた喜び、この喜びが御心がこの地で実現することであり、教会の原動力なのです。
■一緒に考えてみましょう
・いなくなった1匹を必死に探すような神の情熱を、どのような形で知っていますか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 14章25-35節
苦難が待っていたとしても
26 わたしのもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分のいのちまでも憎まないなら、わたしの弟子になることはできません。
27 自分の十字架を負ってわたしについて来ない者は、わたしの弟子になることはできません。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 「家族を憎む」とは
家族を憎みなさいという言葉をイエスから聞くのは、かなり衝撃的かもしれません。
「憎む」という表現を理解するには、2つの選択肢があって、どちらを選ぶときに、
「一方を愛し、他方を憎む」という言い方をしたという知識が必要になります。
ここでは神、もしくは、イエスを愛することが省略されていて、それと比べて、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、
さらに自分は神と比べたら、愛としては優先順位が下がる。神様をより愛する。
そういう選択をしなさいという言葉です。これがイエスの弟子として生きるということです。
- 自分の十字架を背負う
「十字架を負って」というイメージは、当時、十字架で殺される人は、殺される日、自分の十字架の棒を死刑場まで自分で担がせるという習慣に由来します。イエスの弟子になる理由として、いい人だから、イエスの弟子として認められるという人は、これまで1人もいません。
私たちは欠けだらけ、傷ついていて、弱い。だから、神の恵みにすがるしかない。
そういう自分の正直な姿を神の前に晒し、人々の前に晒す準備ができた人が、イエスの弟子として、生きることができるのです。
- 弟子になることを計算する
この2つの話、塔を建てることと戦争するかを決断する王の話は、決断する前に、座って計算することが大切だと言っています。
これはどういう関係があるかというと、イエスの弟子になること、もしくは、イエスの弟子にならないことについて、ちゃんと計算しなさいという勧めです。
弟子たちが頼ることができるべきは、自分の弱さにもかかわらず、共にいて、支えてくれるイエスです。
財産への執着を捨てるのも、そのためだと言えます。
■一緒に考えてみましょう
・クリスチャンとしての「塩気」を自分は失っていないでしょうか。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 14章15節
あなたも神のパーティーに
15 イエスとともに食卓に着いていた客の一人はこれを聞いて、イエスに言った。
「神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょう。」
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 神からの招待を断る人たち
皆が、同じように断るなんて、あり得ないことでした。しかも、どれも盛大な宴会を断る理由に値するとは思えない理由なのです。
まだ話は続きますが、「神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょう」と言った人たちへのイエスの警告が読み取れます。
神の国で食事をするなんて、なんて幸せだと口では言いながら、招かれていたにも関わらず、あなたは断るではないかと。
イエスが招待するのをやめたのではなく、彼らが自分で招待を断ったのです。
私たちは神の国の食事の招待に気づかずに、自分の都合を優先させてしまうことはないでしょうか。
- 文字通り、誰もが招かれている
この主人の夕食会には、たくさんの席があります。だから、もっと多くの人を招くことができます。
そこで、街道や垣根のところまで行きなさいと言われます。街道というのは、町と町を結ぶ道路のことです。
垣根というのは、おそらく町の外にあるぶどう畑の垣根を指すだろうと言われていて、
街の中の人では足りず、街の外まで行って、人を連れてきなさいと主人は言われたのです。
街の外の人となると、同じ民族ではない可能性があります。
また、街の外に追いやられた社会的に立場の弱い人たちも含まれます。イエスの福音はこのように広いのです。
- 恵みを受ける人とは
食事をするというのは、親しさの象徴ですから、普通は、人を選んで、一緒に食卓を囲むのです。
しかし、この家の主人は、誰でも食卓に客として加えます。
つまり、食卓の友として数えるには、あまりに汚れているとか、あまりにもみじめだとか、決して言わないのです。
これは私たちが何度も、繰り返し、確認すべきことです。神が恵みを示して、それを受け取る人は、誰もが恵みの食卓に加えられるのです。
ただ、神の招待を断るかどうかは私たち次第なのです。
■一緒に考えてみましょう
・神のパーティーにふさわしい人とは、どのような人でしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 14章1-2節
こだわることですか
1 ある安息日のこと、イエスは食事をするために、パリサイ派のある指導者の家に入られた。
そのとき人々はじっとイエスを見つめていた。
2 見よ、イエスの前には、水腫をわずらっている人がいた。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- その人も「神の子供」
水腫の病気の人は、欲望に負けた人、罪や汚れのために神から裁きを受けた人と見なされていたかもしれません。
そうだとしたら、神はこのようなタイプの人を癒すのでしょうか。
安息日に、自分の子供や家畜が井戸や穴に落ちたら助けるのに、この病人を癒すことには反対するのでしょうか。
パリサイ派の人たちにとっては、「自分の」子供でも、家畜でもないから、急がなくていいということでしょうか。
そうではないですねとイエスは暗に伝えるのです。
- 人からではなく神からの名誉を
7-11節でイエスは宴会で恥をかかないようにする方法を教えたいのではありません。
賞賛を浴びたいという誰もが避けて通れない願望をどう扱ったらいいのか示しているのです。
神を忘れて、ひたすら他人から名誉を求めることがあります。人からの評価に私たちは支配されることがあります。
思い出したいのは、誰からの評価を私たちは日々、気にしなければいけないかということです。
誰の声に常に注意を払うべきなのでしょうか。
「神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者に恵みを与えられる」これは聖書が一貫して述べている神の原理です。
- 私たちが目を向けるべき人たち
キーワードは「お返し」という言葉です。「誰からお返しをもらうか」です。神に祝福された友情があり、家族関係があります。
それは良いことです。ただ、注意しなければいけないのは誰に目を向けるようにと言われているかということです。
「貧しい人たち、からだの不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たち」を招きなさい。
自分の関心だけでなく、関心の外にいる人たちにも目を向けるようにと私たちは招かれています。
■一緒に考えてみましょう
・私が、こだわるべきことは何でしょうか。反対に手放すべきこだわりは何でしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 13章33節
使命からブレない
33 しかし、わたしは今日も明日も、その次の日も進んで行かなければならない。
預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ないのだ。』
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 先延ばしにしないで
とても興味深い質問から、今日の会話は始まります。「主よ、救われる人は少ないのですか」(23節)。
イエスは少ないとも、多いとも答えませんでした。戸はやがて閉まるのです。
ですから、先延ばしにしないで、戸が開いているうちに決断しなければいけません。
イエスと食事をしたか、教えを聞いたかどうかは問題ではなく、イエスのメッセージを聞いて、悔い改めて応答することが大切なのです。
私は大丈夫かと心配になるような話題かもしれません。
- イエスのブレない生き方
「預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ないのだ。」(33節)これがイエスの覚悟です。
神から託された使命に従う姿です。たとえ、大きな苦しみが伴おうとも、死が待ち受けていると分かっていても、決して逃げ出さない生き方です。
神がずっと願い続けてきたことは、神の民を守り、世話し、育てることでした。
しかし、エルサレムの街に代表される神の民は神の願いを聞かず、神の翼の下に入ることを拒んできたのです。
イエスを救い主として認めない彼らの判断によって、神から見捨てられる道を自分たちで選んだのです。
- 私たちのすべき努力とは
「狭い門から入るように努めなさい」(24節)。これは、私たちの根性が試されているのではありません。
「人にはできないことが、神にはできるのです」(18:27)とイエスは言います。
気合いと根性で乗り越えるのではなく神から恵みをいただき、私たちは救われるのです。
人に求められる努力とは、神の声に耳を傾け、恵みに応答する努力です。
復活のイエスがペテロに、私を愛しますか?と問われるように、私たちもイエスを愛するか問われているのです。
■一緒に考えてみましょう
・「狭い門から入るように努めなさい」は今日の私にとって、どのように響くでしょうか。しばらく祈ってみましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 13章18節
祝福を見つけるコツ
そこで、イエスはこう言われた。「神の国は何に似ているでしょうか。何にたとえたらよいでしょうか。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 「安息日」をどう理解するか
働くのは6日間、安息日には神の前に手を止め、神を礼拝する。
これは安息日の基本的な理解です。会堂司と呼ばれる人からしたら、イエスは聖書に書いてある原則を曲げているように見えたでしょう。
申命記5:15には、奴隷から解放されたことを祝うのが安息日の一つの目的だと記されています。
アブラハムの娘を悪い霊から解放し、神を礼拝することは、安息日にふさわしい行為なのです。
安息日の癒しに、神の国の本質が隠されているとイエスは言います。
- からし種とパン種と神の国
パン種とは、旧約聖書では聖さの反対側にあるものです。登場人物は男性ではなく、女性。
神殿が聖なる場所の代表だとしたら、家の中は日常の場所です。
イエスはあえて、パン種・女性・家という日常の中に神の国を見つけるようにと言われるのです。
これは当時の常識とは、大きく違っていました。このような場所で神の国を見つけなさいと私たちは招かれているのです。
立派なレバノン杉ではなく、小さなからし種に目を向けるように、聖さと俗とがあるなら俗のイメージを使って、イエスは神の国を表現されたのです。
- 期待する形とは違うかもしれない神の国
長く教会にいればいるほど会堂司のような反応をするかもしれません。
ですから、自分が違和感を感じるとき、立ち止まる余白を持ちたいなと思うのです。
違和感を神の前に差し出し、私の聖書の常識は神の心を表しているでしょうか?と一つ一つ、気になった時に、立ち止まり、祈っていく余白を持ちたいなと思います。
聖書をよく知っている宗教指導者たちは、嫌な顔をするかもしれないようなところに、神の祝福は隠れているかもしれないのです。
■一緒に考えてみましょう
・私たちは神の国をどのような形で実現していることを期待しているでしょうか。
もし、私たちの期待と違う形で、神の国が提示されたとき、どのように応答したらいいでしょうか。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ヨハネの手紙第一 4章19節
愛を知り、分かち合う
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
1. ここに神の愛が
神がひとり子、イエス・キリストをこの世界に遣わしました。
イエスは私たちの罪のために(そして、この世すべてのために)、身代わりに、十字架で神に捧げられた「いけにえ」だと聖書は教えます。
イエスが私たちの身代わりになり、罪の罰を受けられたので、私たちは罪に責任を負わなくてよくなったのです。
罪は私たちを苦しめません。罪の呪いから解放されました。イエスの十字架のいけにえに基づく罪の赦しが神の愛の本質なのです。
ここに神の愛があると言われます。
2. 互いに愛し合いなさい
イエスが示した神の愛は、他者のために自らを捧げる生き方でした。
イエスの愛に本当の意味で触れるなら、イエスのように私たちも他者のために、自らを捧げるという神の愛を分かち合う道を歩き始めることになります。
これが神から新しい命をいただくということであり、神がキリストにおいて私たちを赦してくださったように、
私たちの赦しを必要とする人々を赦すという神の愛を分かち合う、新しい人生を生きるということです。
3. 聖霊の導きの中で
今日はペンテコステを記念する礼拝です。聖霊が神から与えられたことを思い出す日です。
すでに神は私たちに御霊を与えてくださっているのです。ですから、私たちは神のうちにとどまることができるし、神も私たちにとどまるのです。
この信仰共同体の中で、私たちは愛することを学んでいるところです。
聖霊の導きに私たちが身を委ね、神の家族を信頼して生きる中で、神ご自身がまず愛を示してくださったように、神のご栄光を私たちに表してくださいます。私たちはこの神の素晴らしさを目撃し、賛美し、証し、神と人に仕えましょう。
■一緒に考えてみましょう
・今日も、神の愛に立ち返りましょう。どのような時間が神の愛に立ち返るのを助けてくれるでしょうか。
神の愛に戻ったら、何に目を向けるようにと促されるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 13章3節
このままで大丈夫?
3 そんなことはありません。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 悔い改めの機会に
おそらく神殿で、いけにえを捧げようとするガリラヤ人をピラトが殺した。これが1節で報告されている内容です。
イエスはピラトのひどい話を聞いて、ローマ帝国に対して怒りませんでした。ガリラヤ人が特別に罪深いとも言いませんでした。
そうではなく、イエスと一緒にいる人たちに向けた警告としました。あなたがたは悔い改めなさい。
どこに向かって歩いているか。何に関心があるのか。あなたの宝のあるところにあなたの心もある。
それは神なのかと、ここまでも繰り返して問いかけてきました。
- 実を結ばないいちじくの木とは
ぶどう畑がイスラエルの比喩として使われるように、いちじくの木はユダやエルサレムを指して使われることがあります。
神はイスラエルが悔い改め、救いの申し出を受け入れることを望まれますが、彼らは頑なに悔い改めないままです。
悔い改めの実を見つけることはできません。神は悔い改め、神のもとに帰ってくるのを待っています。
まだか、まだかと待っていますが、いつまでも待っているわけではない。神の裁きのタイミングが来るから、注意しなさい。
- 実を結ぶのを待っている神の種
私たちの関心はそれぞれ違うかもしれません。それは多様性です。違っていていいのです。
一致すべきは、主に立ち返り、主の声に耳を傾け、信仰の旅に出ることです。
神と人を愛するために何が託されているでしょうか。示されているかもしれないと感じることがあったら、分かち合ってください。
神様のやりたいことの種はすでに蒔かれているものです。芽が出るのを待っている種があるかもしれません。
皆さんのビジョン、願いを聞かせてください。
■一緒に考えてみましょう
・神に管理するようにと託されている思いやビジョン、願いの種はあるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 12章37節
急な来客、大丈夫?
37 帰って来た主人に、目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。
まことに、あなたがたに言います。主人のほうが帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- いつ神が来ても大丈夫?
イエスは私たちが想像していないような時に、想像していない姿で、すでに目の前にいるかもしれないのです。
私たちは無意識のうちに計算することがあります。「今日はまだ主人は帰ってこない」そういう時に、人に敬意を欠けることがあるのです。
特に自分よりも下の立場と思う人に敬意を表さないことがあるかもしれません。
誰にも見られていなかったら、ずるしたくなることがあるかもしれません。それが私たち人間の本質です。
いつ神に見られても大丈夫な生活をしなさいと、はっきり警告されているのです。
- 平和ではなく分裂
平和ではなく分裂。過激な言葉に驚かされますが、イエスは表面的な平和、見せかけの平和に満足しません。
イエスは課題があれば、課題に直面させます。抜き打ち検査のような突然の訪問を私たちはあまり歓迎しないかもしれませんが、真実を晒します。
これが福音を語るという一つの側面です。対立は避けて通れませんが、対立が目的ではありません。
罪に妥協したり目を逸らしたりするのではなく、救われること、解放される道をイエスは用意します。
- 天気は読めるのに、なぜ?
天気は読めるのに、なぜ天の神の御心を見分けようとしないのか。これもまた警告の言葉です。
あなたの心のあるところにあなたの宝もあると前回、読みましたが、本当に私の心が惹きつけられていることは何でしょうか。
神に託されているものの忠実な管理人でしょうか。
58-59節は、神の裁きはすでに始まろうとしているという警告です。
でも、まだ間に合うというメッセージです。神様はいつも待っていてくださいます。
■一緒に考えてみましょう
・私に神様は何を管理するように託しているでしょうか。私は忠実な管理人でしょうか?
説教者:片山 信彦 兄
聖 書:コリント人への手紙第二6章2節
見よ。今は恵みの時
神は言われます。
「恵みの時に、私はあなたに答え、 救いの日に、あなたを助ける。」
見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
1. 出エジプト記3章1節~5節
モーセはミデヤンという場所で羊を飼って生活していました。その場所で、「ここに近づいてはいけない。あなたの履物を脱ぎなさい。
あなたの立っている場所は聖なる場所だからです」という神様からの語りかけを聞いたとあります。
(5節)モーセは同胞のイスラエル人がエジプトで苦役を受け、差別され苦しんでいる状況を見て正義感から立ち上がりました。
その結果エジプト人を殺してしまい、それがかえって同胞の不信を買うことになり、身の危険を感じて、ここミデヤンの地に逃れてきました。
自分は、苦しんでいる人を助けようという正しい動機、正義感から行ったのに、なぜ身の危険を感じるようなことになるのか、
自分は悪いことはしていないのに、という思いを持ちながらミデヤンに逃れてきました。
ですから、ミデヤンに逃れてきたモーセにとっては、もはや神を信じることができない者になっていたのではないかと思います。
ですからモーセにとっては、失意と絶望、神のいない所、そこがミデヤンだったのです。
現代の私たちも似たような気持になることがあります。戦争があちこちで起きています。
国が滅びそうな時代を見て嘆き、差別や不公正がはびこる社会を見て絶望し、他者の言葉や行動を見てつまずき、自分の弱さを見て泣くこともあります。
その中で、自分の考えしか頼れない、他人は宛てにならない、自分の考えだけが信用でき、自分の思うとおりに生きるしかない、
神様なんていない、と思ってしまうこともあります。これが私たちの現実です。
その意味で私たちの今、現実はミデヤンだと言ってもいいくらいです。
2. でも、このミデヤンの地でモーセは、あなたの立っている場所は聖なるところです。
聖なる地なので、当時の習慣として清い場所では履物を脱いだようですので、
本当にここは聖なるところなので履物を脱ぎなさい、という語りかけを聞きました。
モーセにとっては、神不在と思える現実の真只中で神様からの語り掛けを聞くことは、
神様不在と思える所にこそ神様はおられる聖なる恵みのあるところだということを経験したのだと思います。
3. 第二コリント6章2節の後半の「見よ、今は恵みの時、今は救いの日です」という御言葉が響きます。
「見よ」とはどこを見るのでしょうか。何を見よ、言うのでしょうか。
「見よ」とは「上を見よ」、ということです。なぜ今が恵みの時なのだろう。なぜ今日が救いの日なのだろうと思う日があるでしょう。
でも、どのような現実であり、どのような自分であっても、その現実に主の恵みと救いが与えられるのだ。その主を「見よ」、というのです。
その救い主なる主を拝する時、それによってどんな現実も愛なる神のうちにあることを知ることができると聖書は語るのです。
主を見上げる時に、恵みと救いを与えてくださる主が共にいてくださることを心から覚え、感謝しましょう。
目を上げて、見て、晴らしい主がいてくださることを喜びましょう!!
4.詩編121:1~2節を連想しました。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。
私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。
ルカの福音書講解
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 12章34節
宝物は何ですか
34 あなたがたの宝のあるところ、そこにあなたがたの心もあるのです。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 自分のことで頭がいっぱい
16-20節に出てくるお金持ちは「私の」という言葉を何度も使っていました。
私の作物、私の倉、私の穀物。私の財産。このお金持ちの生き方、ものの見方が「私の」という言葉に表れています。
彼の人生は、自分のことで頭がいっぱいです。
溢れるばかりに祝福され、たくさんの収穫を手に入れたとき、神を愛し、人を愛するという生き方について彼は考えたでしょうか。
彼は自分のことだけ考えていました。目の前の財産を信じ、神を無視した人生でした。
- 心配に振り回されない
後半は神に全面的に信頼して大丈夫だという話です。私たちはさまざまな心配に囲まれているかもしれません。
イエスに従うと決めたら迫害されるかもしれません。
安全に暮らせたとしても、お金や食べ物、着る物、生活のために必要なものは、たくさんあるでしょう。
しかし、神は心配するのをやめなさいとはっきり言います。
神は恵み深いお方であり、神が満たしてくださるから、心配しなくて大丈夫だというのがイエスの約束です。
- 天に宝を積む「施し」
神に宝を蓄える方法が最後に明らかにされます。施しをすることです。
これは恵みのリズムで生きることです。神から恵みをタダでいただいたら、その恵みを次の人に手渡していくということです。
自分のことだけ考えて、視野が狭くなり、神や周りの人が見えなくならないようにするのが「施し」です。
施しのための出発点は、まず神が私たちを愛してくれているということ。
神の愛を思い起こすことが、神と周りの人に恵みを分かち合うことにつながります。
■一緒に考えてみましょう
私たちは一度、立ち止まりたいと思います。私たちは何を求めて、何を貯めようとしているでしょうか。
倉があるとしたら、そこに何が入っているでしょうか。
自分のことだけ考えて生きているのか、神と人を愛することを考えながら生きているのか、しばらく振り返ってみましょう。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 12章6節
神はあなたを忘れない
6 五羽の雀が、二アサリオンで売られているではありませんか。そんな雀の一羽でも、神の御前で忘れられてはいません。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 誰を恐れるべきか
ここで初めてルカの福音書では、イエスが弟子たちを「友」と呼びます。
本当に大切なことを打ち明ける前に弟子たちを友と呼びました。
イエスが伝えたかったのは、誰を恐れるべきかです。神を恐れなさいという呼びかけが、繰り返されます。
数々の預言者、イエスの時代ではバプテスマのヨハネが殺されたように、
神に遣わされ、神の言葉を語るというのは、この世界から拒絶され、黙らせようとプレッシャーをかけられ、
時に、殺されることもある。そうであっても、恐れるべきは人ではなく、神なのだというのが友イエスからの正直な言葉なのです。
2.神は決して私たちを忘れない
当時、スズメは安く手に入るものでした。
小さなスズメを神が忘れないとしたら、なおのこと、神のイメージに造られた人間を神は決して忘れることはないのです。
これがイエスと父なる神との関係を確かに保証し、イエスは安心して、自分の使命を全うすることができたのです。
私たちが人々の前で、また隠れたところで、イエスを認めるのか、知らないというのか、どちらでしょうか。
私たちの態度がイエスの私たちへの判断に反映されるのです。
- 迫害への備え
聖霊が何を言えばいいか、助けてくださいと私たちが求めるとき、ちゃんと、その時、言うべきことを言わせてくださるというのが聖書の約束です。
私たちがイエス・キリストの弟子ならば、迫害や試練は避けて通れないものなのです。
だからこそ、お互いのために、祈ることができたらと思います。
新約聖書の中に何通も手紙が保存されたパウロも手紙の最後でよく教会の人たちに、私のためにも祈ってくださいと書いていました。(エペソ6:19など)
■一緒に考えてみましょう
・「神は私を忘れない」という真理を私たちが日々、思い出すために、どのような霊的な習慣が役に立つでしょうか。
・今、私はどのような祈りの助けを必要としているでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 11章39節
内面を磨こう
39 すると、主は彼に言われた。「なるほど、あなたがたパリサイ人は、杯や皿の外側はきよめるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 的外れな信仰
パリサイ人たちはモーセの律法を守るために、自分たちで考えたルールを律法に付け加えていました。
今回の「きよめの洗い」という習慣もパリサイ人の考えたルールの一つでした。
パリサイ人の考え方を明らかにするため、イエスはあえてそれをしませんでした。
パリサイ人が信じているルールを守ることが彼らの関心事になっていて、神の心、思いは後回しにされているという現実です。
旧約の時代から預言者たちが警告していたように、正義と神への愛を疎かにして、表面的な、目に見える部分だけ信仰的な行動をしても、それは的外れな信仰なのです。
2.重荷を負わせるか、重荷を背負うか
「おまえたちもわざわいだ。律法の専門家たち。人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分は、その荷物に指一本触れようとはしない。」(11:46)
イエスの指摘は、私たちの信仰生活を振り返るきっかけをくれます。私たちの経験が周りの人への証になります。
イエスと一緒にいて、重荷が軽くなることを体験しているでしょうか。
それとも、クリスチャンとなることは重荷となるような信仰生活を送っているでしょうか。
本来イエスは重荷を背負ってくれます。
- 厳しい現実を突きつけられたあと
パリサイ人も律法学者も思わぬタイミングで、イエスからバッサリ切られた結果、激しい敵意を抱き、イエスとはっきりと対立するようになりました。
偽善、さほど大事でないことにこだわり、本当に大事なことを後回しにする。神の正義や愛が後回しにされ、他のことに関心が向いている。
人々を本物に導いているつもりが、逆に邪魔をしている。これらの厳しい言葉を、私たちは復活の光の中で自分を救い出す言葉として、受け止めることができるでしょうか。
■一緒に考えてみましょう
・復活の光の中で、この厳しい現実に目を向けることができますように。
イエスの叱責は、パリサイ人も律法学者も激しい敵意を引き起こしましたが、私たちはどう反応するでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 24章6節
三日目によみがえる
22 ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたころ、主がお話しになったことを思い出しなさい。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 復活の朝の正直でリアルな記録
日曜日の明け方早くに、女性の弟子たちはイエスの墓に向かったのです。
すると、墓の石がわきに転がされ、主イエスのからだは見当たりませんでした。彼女たちは途方に暮れます。
この段階でも、復活ということを、誰も期待していませんでした。これが私たちにも通じる、正直で、リアルな記録です。
神様は私たちと一緒に神の働きに加わることを喜んでくださいますが、私たちが神の働きを信仰をもって応答できるとは限らないのです。
- 御使いによる決定的な言葉
御使いの言葉によって、イエスの墓がなぜ空なのかという理由が明らかにされます。クリスマスの前と似ています。
どのようにして復活が実現したのかは語られていません。
ただ、イエスが父なる神によってよみがえられたということが神の使いによって告げられます。
復活は神の神秘に属することです。私たちはこのプロセスを理性的にたどることはできません。
「イエスの言葉を思い出しなさい。そして、神の力の大きさと神の約束の確かさにあなたは信頼しますか?」と私たちは問われるのです。
- 目に見えるヒントはわずか
女性の弟子の驚くべき言葉を聞いても、弟子たちの心はまだ閉ざされたままで信じられませんでした。
イースターの朝、弟子たちは絶望の中にいました。
目の前で、すでに驚くべきことが起こっているにもかかわらず、真実として受け止めることができないままでした。
ペテロは立ち上がって、墓まで行きました。確かにそこにあったのはイエスの体を包んでいた亜麻布だけが残っていたのです。
目に見えるヒントはそれだけなのです。空の墓と亜麻布だけです。
■一緒に考えてみましょう
1ペテロ1:3には、復活によって私たちを新しく生まれさせてくださると記されています。
イエス・キリストの復活の新たないのちに生かされると、私たちはどう変わるでしょうか。
説教者:蒔田 望 牧師
聖 書:ルカの福音書 13章22節
エルサレムへの旅
22イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。
聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会
■アウトライン
- 何に目が留まるか
この1年も礼拝では、ルカの福音書を読んでいきます。ルカの福音書の後半のテーマはエルサレムへの旅です。
エルサレムとはイエスが十字架にかけられるところです。1年かけて、イエスのエルサレムへの旅を一緒に歩きたいと思います。
イエスの旅というのは、目的地に急いで着くことを最優先にしているわけではありません。
このイエスの旅を一緒に歩きながら、私たちはそれぞれ何に注意が向くのか、
神様は何を見せようとしているのか、ぜひ祈りつつ、歩けたらなと思っています。
- イエスが熱望した食卓
イエスは過越の食事をしたかったと語ります(ルカ22:15)。イエスは食事の交わりを本当に大切にする文化の中で暮らしていました。
その中でも、この食卓は特別でした。過越の食事という神様がエジプトから救い出してくださったことを記念する食事でした。
もう1つ特別だったのは、この食事は弟子たちとイエスのために準備された食事だということです。
イエスが過越の子羊としていけにえになることを伝え、それを食べ、飲み、祝福に加わるように招きます。
- 誰もが招かれている
どれだけ私たちはボロボロでみすぼらしく、情けない姿だとしても、イエスは私たちのために命を差し出してくださいます。
新しいいのちを与え、罪を洗い流します。あなたは神の大切なこどもだということを、この杯を飲みながら、思い出すようにと語られます。
裏切る人の手もテーブルの上にあるように、この世界は未だに混沌としています。これが私たちの生きていく世界です。
イエスを覚えて、これを行うとは、イエスが生きたように、私たちも神の御霊に導かれ、混沌とした世界に自分自身を差し出していくということです。
■一緒に考えてみましょう
・イエスの食卓に私が招かれるとは、どのような意味が私にあるでしょうか。どのような祈りが心から溢れてくるでしょうか。